当ページでは、人・猫同士に分けて噛む理由・原因、噛む猫の特徴や噛まれた際の対処法なども紹介していきます。
猫に噛まれると悩んでいる人は、ぜひお役立てください。
猫が人の手や足を噛む理由や原因は?
猫が人の手や足を噛む理由を10個見ていきましょう。
猫を飼っている人は、知っておくと、いざ噛まれた時にも冷静に対処できます。
理由①本気で噛むのは獲物を獲る本能的な行動
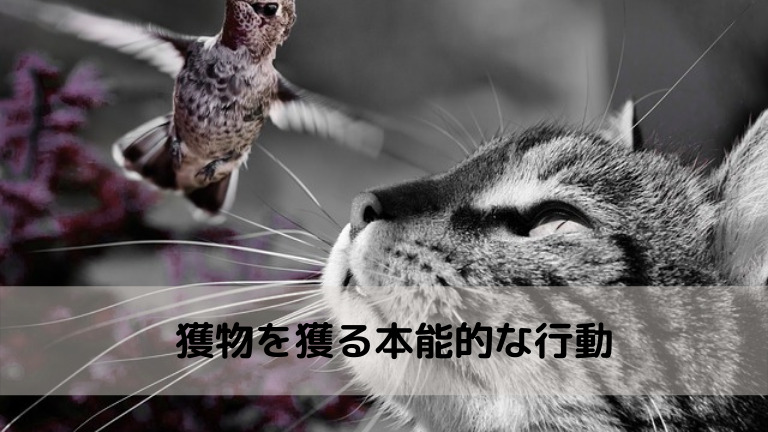
甘噛みでは無く本気で噛む場合は、飼い主のことを獲物として見ているかもしれません。
猫は獲物を獲るために、噛む・引っ掻くなどの元々の本能的な行動・反応が備わっています。
手や足を動かして飼い主からすると遊んでいるつもりでも、猫からすると“獲物”と認識している可能性が高いです。
理由②痛みや恐怖を感じたり驚いたりして噛む(防衛行動)
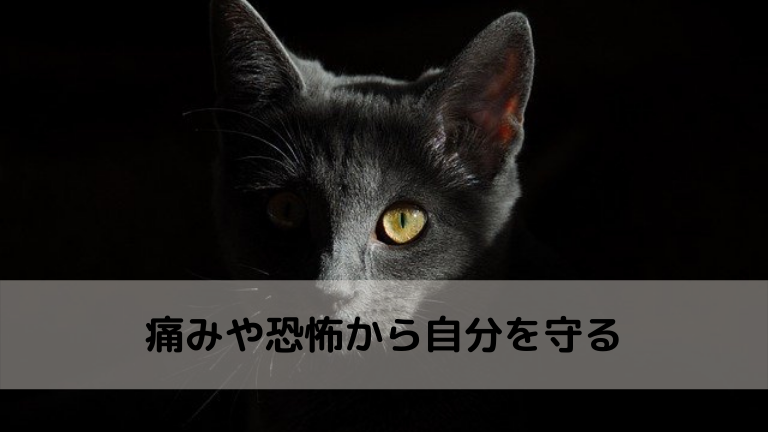
噛む理由2つ目は、何らかの痛みや恐怖を感じたりしている場合です。噛むことで、痛みや恐怖から自分を守っているのです。これを防衛行動と言います。
猫は非常に警戒心が強く、少しでも自分に恐怖を感じたらすぐに噛みつきます。また驚いた時にも本能的に噛みます。
野良猫を触ろうとして威嚇されたことは無いでしょうか。その反応も、この防衛行動から来ています。
理由③甘噛みやキックは愛情表現?要求や遊んで欲しいから
噛み方が甘噛みだったり、キックされたりする場合は、「遊んで欲しい」「何かをして欲しい」と要求していることもあります。
猫は動くものに本能的に反応するので、手を振ってじゃれ合っている時に甘噛みされた時は、手をおもちゃだと判断して「もっと遊ぼう」と言っているのです。
遊べる相手だと信頼したゆえの愛情表現とも言えますが、「手=おもちゃ」と認識すると、噛む強さもエスカレートすることがあります。
遊ぶ時は、なるべく猫用のおもちゃを使うようにしましょう。
また、離乳が早かった子猫は、母猫のお乳を吸う感覚で、人の手や指を甘噛みすることが多くなるようです。
痛く無ければ無下に止めさせなくて良いので、痛いと感じたらアクションしてきちんと教えることが大切です。
理由④何もしていないのに噛むのはストレスが原因かも(しっぽ噛みも)

自由奔放に生きている猫とは言え、人間と同じようにストレスも感じます。
特に何もしていないのに自分の尻尾などを噛んでいる場合は、何かしらのストレスを感じて発散しているかもしれません。
慣れ親しんだ家から引っ越したり、家族が増えた時などによく見られ、猫が過ごすスペースに不満を感じている時などにも出やすいです。
特に赤ちゃんが生まれると皆が付きっ切りになり、自分の相手をしてくれない=寂しいと感じて噛むこともあります。
猫は意外にも環境の変化に敏感なので、いつも以上に気に掛けてあげたり、引っ越す場合は今まで使っていた物も持って行くなど、できるだけストレスを感じないように注意しましょう。
理由⑤止めて欲しい!の合図

猫は言葉を発することができないので、撫でている時でも「止めて欲しい」と感じたら噛みます。
猫は長時間撫でられたり抱かれることは好まないため、猫が自分から触って欲しいと寄ってきたのに噛む場合は、「止めて欲しい」という意味です。
これは愛撫誘発性攻撃行動とも言い、噛まれないようにするには、飼い主自らが“猫が発するサイン”を察するしかありません。
もちろん個体差があり、長時間撫でられたり抱かれることが平気な猫もいるので、すべての猫に当てはまるわけではありません。
理由⑥発情期だから
去勢していないオス猫であれば、発情期が理由で噛んでいるのかもしれません。
オス猫は、交尾時にメス猫が動かないように背中を噛む「ネックリップ」と呼ばれる行動を取るため、噛むもの=メス猫に見立ている可能性もあります。
発情期が理由で噛んでいる場合は、去勢すれば治まります。
理由⑦またたびに酔った
猫は、またたびの匂いをかぐと体を擦りつけたり、よだれを垂らすなど興奮します。中には酔っ払った状態になる猫もいます。
またたびに酔った猫は訳が分からなくなっている状態なので、いくら離そうとしたり、叱ったりしても効果がありません。
時間が経てば治まりますが、またたびを与えると酔うこともあることを知っておきましょう。傍で様子見しつつも、手や足は出さないようにしてください。
理由⑧大人の猫で噛み癖があるのは要求が叶うと思っているかも
大人の猫が噛むのは、噛み癖が付いていることがほとんどです。
噛むたびに遊んだり、おやつをあげたりなどしていると、噛めば自分の要求を満たしてくれると認識して、噛むことを止めません。
噛み癖を付けないためには、子猫の時から『噛むと要求が叶う』経験をさせないようにすることが重要です。大人になってからだと、矯正はかなり難しいです。
理由➈病気やケガが原因で噛む
病気やケガをしていると、その痛みや不快感を発散するために噛むことがあります
ある特定の場所を触ると噛むなど規則性がある時は、迷わず動物病院に連れていきましょう。
また普段温厚だったのに急に噛むことが増えた場合にも注意が必要です。脳や甲状腺の病気が隠れているかもしれません。
手遅れになる前に、常日頃から飼い猫の状態や行動パターンを観察して些細な変化も見逃さないようにしてください。
理由➉猫が噛む人を選ぶ?特定の人を噛むのは兄弟と勘違い?
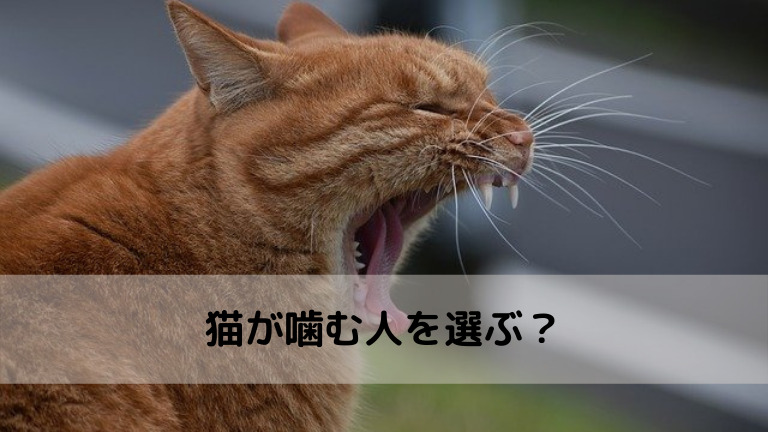
猫が家族の中である特定の人だけを噛んでいるとすると、兄弟と勘違いしている可能性もあります。
ペットショップから迎え入れた猫の場合、猫同士で噛み合った経験がないので加減が分からず、血が出るほど噛んだりする子もいます。
甘噛みならば良いですが、あまりに強い力で噛まれる場合は、放置してみましょう。構うから噛むならば、敢えて全く相手にしなければ自然と治まってくることも多いです。
猫同士で噛む理由や原因は?
猫同士で噛む場合はどのような理由が考えられるのでしょうか。
人とはまた違う理由が2つあります。確認していきましょう。
理由①子猫同士が噛み合うのはじゃれ合い
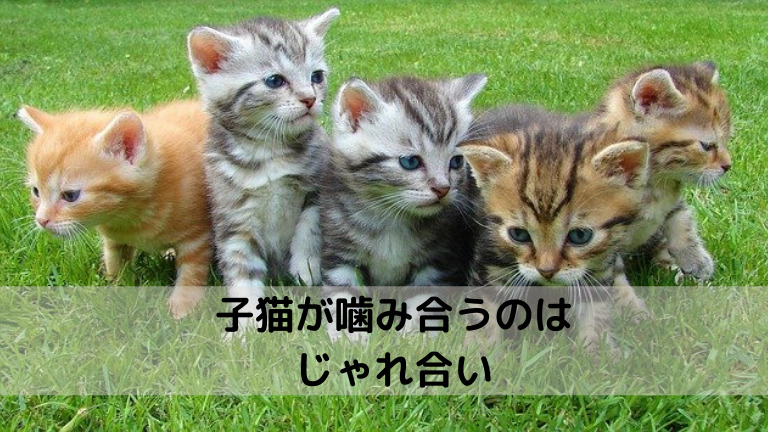
子猫同士が噛み合っているのは、気にしなくても良いです。噛み合うよりも“じゃれ合い”で、猫同士のコミュニケーションの一環だからです。
前述したように猫は噛み合うことで力加減や痛みを学びます。爪を立てたり、本気で噛んでケガをしたり、血が出るほど噛むことはほとんどありません。
理由②大人の猫同士が噛み合うのはマウンティング
大人の猫同士が噛み合っている場合は、子猫のようにじゃれ合うコミュニケーションでは無く、マウンティングといって「自分の方が強い」と相手にアピールしています。
既に飼っている猫が居て、2匹目を迎え入れたとしましょう。
最初に飼われている猫が新しく来た猫に対して噛むのであれば、自分の立場を優位にしたいがためにマウンティングを行なっていると言えるでしょう。
猫同士が噛み合ったらどうしたら良い?
子猫でも成猫でも、猫同士が噛み合っている時は、飼い主としてどうすれば良いと思いますか。
じゃれ合いで、成長する上での大切な過程です。無理に引きはがさず見守っていてください。近くに母猫が居れば、きちんと仲裁します。
威嚇しながら噛み合っているのでなければ、放置で構いません。また噛まれた相手の猫が噛むのを止めた場合も、問題無しです。喧嘩ならば必ず噛み返して応戦するからです。
猫がソファや家具を噛む理由や原因は?

猫が、人や猫では無く、ソファや家具など硬いものを噛む時にも理由があることを知っておきましょう。
理由①ソファや家具をおもちゃにして遊びたい
単にソファや家具をおもちゃにしたいと思った時も、噛みます。
猫は好奇心が強い動物なので、動かないものであっても、初めて見るものには興味を示します。子猫に多く見られ、遊びたい故にソファや家具を噛んでいるわけです。
せっかく新調したソファも噛まれてボロボロ‥、飼い猫が居るご家庭では少なからず経験しているのでは無いでしょうか。噛むだけで無く、爪とぎされることも多いです。
理由②ストレス発散のため
ストレスが溜まっている猫が、ソファや家具を噛んで発散しているのかもしれません。
ストレス発散で噛んでいる時に無理に止めさせるとさらにストレスが溜まり、噛むのがエスカレートすることも少なくないので、理由を見極めるのが肝心です。
理由③歯が痒くて違和感がある
子猫が家具を噛む場合は、歯が生え変わるなど歯や歯ぐきが痒い・違和感が生じている可能性があります。噛むことで、この違和感を少しでも紛らわそうとしているのです。
噛みやすい猫の特徴
噛みやすい猫には特徴があります。なかなか噛むことを止めないならば、以下の特徴に当てはまっていないか確かめてみてください。
特徴その①野良猫で人間慣れしていない

家に迎え入れる前に、その猫はどのように過ごしていましたか。保護猫やペットショップでは無くて、野良猫では無いでしょうか。
野良猫は自分が食べる物の確保や縄張り争いなど、過酷な環境で生きています。
それゆえに警戒心も強い猫が多いので、人間には恐怖心を感じてなかなか心を開かずに噛む行動が起こりやすくなります。
しかし飼って信頼関係を構築していくことで、だんだん噛む頻度が減っていきます
筆者の実家で飼っている猫も野良猫でしたが、打ち解けて今ではとても穏やかでほとんど噛むことはありません。
特徴その②元々の性格が攻撃的
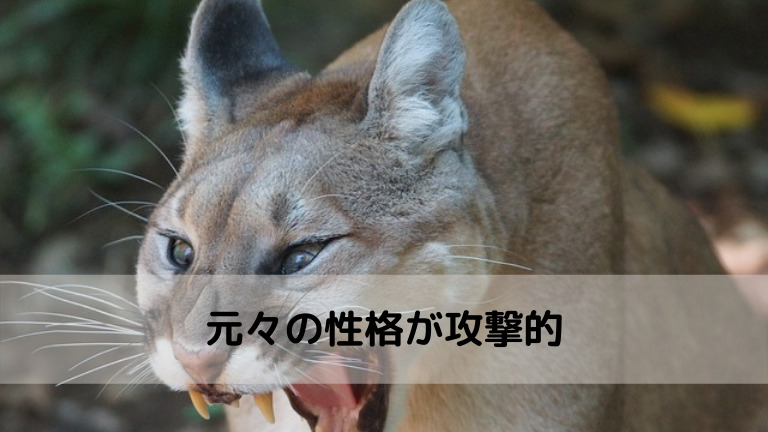
猫もそれぞれ性格が異なるので、元々攻撃的である猫は噛みやすい傾向があります
実際に飼ってみないと分からない部分ですが、メス猫よりはオス猫の方が噛みやすいと言われています。
特徴その③子猫
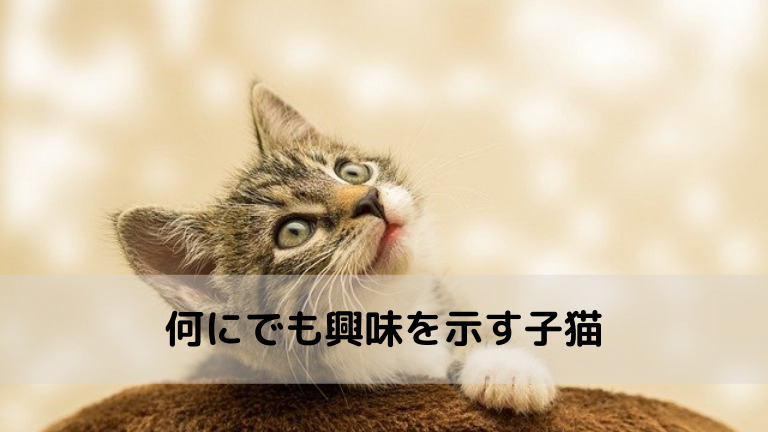
子猫はとにかく目に入るものは何にでも興味を示します。人・物に関係無く噛むので、困っている人も居るかもしれません。
しかし噛むことで、やって良いことや悪いことなどを含めて色々なことを学んでいます。成長していけば自然と治まるので、よほどのことが無い限りは噛ませてあげましょう。
猫の甘噛みで病気になる?噛まれると人は感染症になる?
猫に噛まれると、場合によっては病気になったりすることもあることを知っておいてください。
甘噛みでそんなに強くないから‥といって放っておくと、思わぬ感染症を引き起こし命の危険にさらされることもあるので注意が必要です。
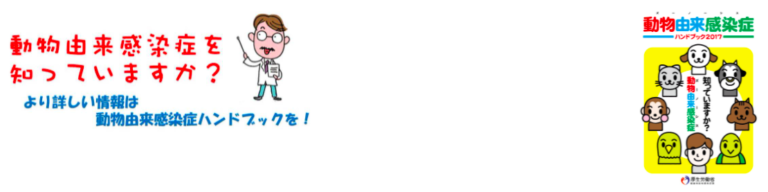
厚生労働省の、動物由来感染症を知っていますか?も参考にしてください。猫だけでなく、あらゆる動物に触れあう際に注意して欲しいことが記載されています。
「動物由来感染症」とは、動物から人間へうつる感染症をあらわす言葉です。
「人獣共通感染症」といった言葉もありますが、厚生労働省は人の健康問題という観点に立って、この「動物由来感染症」という言葉を使っています。
人への感染症については医学が対応し、動物の感染症については獣医学が対応していますが、動物から人へ伝播する動物由来感染症については、医学と獣医学が協力して対応することが大変重要です。
引用元:厚生労働省 動物由来感染症とは?
パスツレラ症
パスツレラ症とは、パスツレラ菌に感染することで起こる病気です。ほぼ全ての猫が、パスツレラ菌を口腔内や爪の中に保有しています。
イヌの約75%、ネコのほぼ100%が口腔内常在菌として病原体を保有しています。
小動物獣医療関係者向け情報
人間がパスツレラ菌に感染すると、数時間程度で傷口が痛み赤く腫れあがって化膿します。
リンパ節の腫れや発熱を引き起こしたり、免疫力が低下しているなどの時は敗血症や髄膜炎・肺炎といった重篤な状態になることもあります。
バルトネラ症(猫ひっかき病)
バルトネラ症は通称「猫ひっかき病」とも言われており、バルトネラヘンセレと呼ばれる菌が、生息しているノミに刺された猫から人間へと二次感染することで起こります。
噛まれると虫刺されのような湿疹が出るのが特徴で、まれにリンパ節の腫れや食欲不振・頭痛なども生じます。軽傷であれば、自然治癒しますが、ひどい場合は脳炎に至る可能性があります。
猫を介して発症することが多いため猫ひっかき病と言われていますが、犬に噛まれても起こります。
カニモルサル感染症
カニモルサル感染症は、カプノサイトファーガという菌の感染症で、猫の口腔内に生息していることが多いです。
発熱・倦怠感・頭痛など風邪に似た症状を引き起こし、悪化すると髄膜炎や敗血症などの全身症状から死に至ることもある恐ろしい病気ですが、日本での発症は少ないです。
Q熱
Q熱は、あまり聞き慣れない病気かもしれません。コクシエラ菌と呼ばれる菌が原因で、インフルエンザのような症状(発熱・筋肉痛・頭痛・下痢や腹痛)が見られます。
重症化すると心内膜炎や髄膜炎、肝臓にまで影響を及ぼす慢性肝炎などを発症するケースもあります。
猫に噛まれた傷口などの対処法
猫に噛まれると必ず上記の病気が発症するわけではありませんが、噛まれたら以下の手順ですぐさま対処してください。
とにかく噛まれたら、何かをやっている途中でも中断して“すぐに”行うことが大切です。
- 1.傷口を流水で丁寧に洗う‥必ず流水で洗いましょう。これでもかというくらい、丁寧に洗ってください。
- 2.傷口を押し出すように洗う‥少し痛いかもしれませんが、傷口の周りを押しながら、中のものを押し出す感覚で洗ってください。できるだけ菌を体内に侵入させないためです。
- 3.傷口を清潔にして消毒する‥十分に洗い流したら、傷口を優しく拭いて清潔にして消毒してください。
溜めた水で洗う/絆創膏をずっと換えないのはNG!
傷口を洗う時には流水が原則です!溜めた水で洗ってしまうと、せっかく洗っても水の方に菌が溜まるからです。常にきれいな水で洗い流さなければ意味がありません。
また消毒後に絆創膏を貼る場合は、絆創膏をこまめに換えるましょう。貼りっぱなしにすると不衛生で、菌が繁殖してしまうこともあるからです。
傷口が小さくても念のため病院に受診を!
本章で紹介した対処法は、あくまでも“一時的な最低限の”方法です。噛まれた側の免疫力低下などで、思わぬ病気を引き起こすこともあります。
そのため、少しでも感染症リスクを減らすためにも、自分でできる対処法を行なった後は、念のため病院に受診して手当てをしてもらいましょう。
猫の噛む力はとても強い

猫は人間よりもはるかに小さいので、噛まれても大したことないと思っている人はいませんか。
猫の噛む力、特に本気モードの時は、体格からは想像できないほどの強さです。
なんと噛む力は100kgに及ぶとも言われており、噛まれると上記の感染症の危険性があるだけでなく、何十針と縫うほどの大けがを負うこともあります。
人間の方が大きくて強いと思ってちょっかいを出すと、本当に痛い目に遭うので注意してください。
猫に噛むのをやめさせる効果的なしつけ方法
猫に噛むのをやめさせるために効果があるしつけの方法を紹介します。子猫の頃からきちんとしつけを行えば、噛むことは少なくなり、噛み癖も減るでしょう。
方法①猫をよく観察して噛む理由を知る
普段の生活の中で、猫をよく観察しておくことはとても効果的です。
第一章で猫が噛む理由を10個紹介しましたが、これらの理由に当てはまるのかどうかも、観察していなければ決して分からないことです。
特に今まで構い過ぎていた人は、我慢して注意深く観察してみてください。こちら(飼い主)が何もしないことで、より噛む理由が何かが分かってくるはずです。
方法②猫用のおもちゃを噛んでストレス発散や遊ばせる

噛んで困っている場合は、猫用の噛むおもちゃを与えて遊ばせてみてはいかがでしょうか。
猫が好む香りやまたたびが含まれたおもちゃなどを選ぶことで、喜んで遊んでくれるでしょう。また、噛んで遊びながらデンタルケアできるものなどもあります。
どのようなおもちゃが良いのか悩みますが、キャットケアスペシャリストが紹介しているおすすめのおもちゃ8選といったサイトも参考にしましょう。
要注意!むやみに怒ったり叩くのはダメなしつけ
猫が噛むのを止めない時にやりがちですが、むやみに怒る・叩くなどでしつけることはNGです。
猫にとっては恐怖でしかないですし、恐怖感を与えるしつけでは信頼関係を作ることはできません。余計に噛む行動が悪化してしまい、手を付けられなくなることもあります。
また噛んで時間が経ってから怒ることも、猫にとっては何で怒られているのか理解できないので控えましょう。噛まれたその時に、冷静に教えることが大切です。
猫の噛み癖にスプレーはおすすめ?

猫の噛み癖がなかなか直らない‥という時は、噛む対象になっている物にスプレーを噴射してみることも選択肢の一つです。
しつけスプレーとも呼ばれていて、猫が嫌がる成分が含まれています。
家具に噴射するもの・人に噴射するもの・猫に直接噴射するもの等、様々な用途のスプレーが販売されているので状況によって選んでください。
ただしすべての猫に有効とは限らず、中には全く気にしない猫も居ます。しかし使わないよりは効果があるので、良く噛む場合は購入して試してみる価値ありです。
猫が見ていないところで噴射しよう
もしスプレーを使う場合は、猫が見ていないところで噴射しましょう。噴射しているところを見られると、警戒して寄り付かなくなることもあるからです。
噛むのを止めるまで繰り返しやってみる
一度スプレーを使ったくらいでは、効果を感じにくいかもしれません。その時は繰り返し、やってみてください。
猫にとって嫌な香り・味であれば、何度か行なうことで「美味しくない」と判断して噛むのを止めるからです。繰り返してやる際は、少し時間を空けるのもポイントです。
まとめ
猫が噛むのには、本能的な行動の他にも次のように様々な理由が考えられます。
- 痛みや恐怖から守るため
- 要求や愛情表現
- 止めて欲しい、ストレスのサイン
- またたびや発情期の影響
- 病気やケガ
また、感染症や大けがを負う可能性も生じるほど、猫の噛む力は強いです。
なぜ噛むのかは、猫の性格や生まれてきた環境などにも大きく左右されます。愛猫を注意深く観察して、まずは噛む理由がどこにあるかを見つけましょう。
その上で原因を取り除きつつ、場合によってはスプレーなどのしつけ用品も有効に使って対処していただければと思います。
]]>

